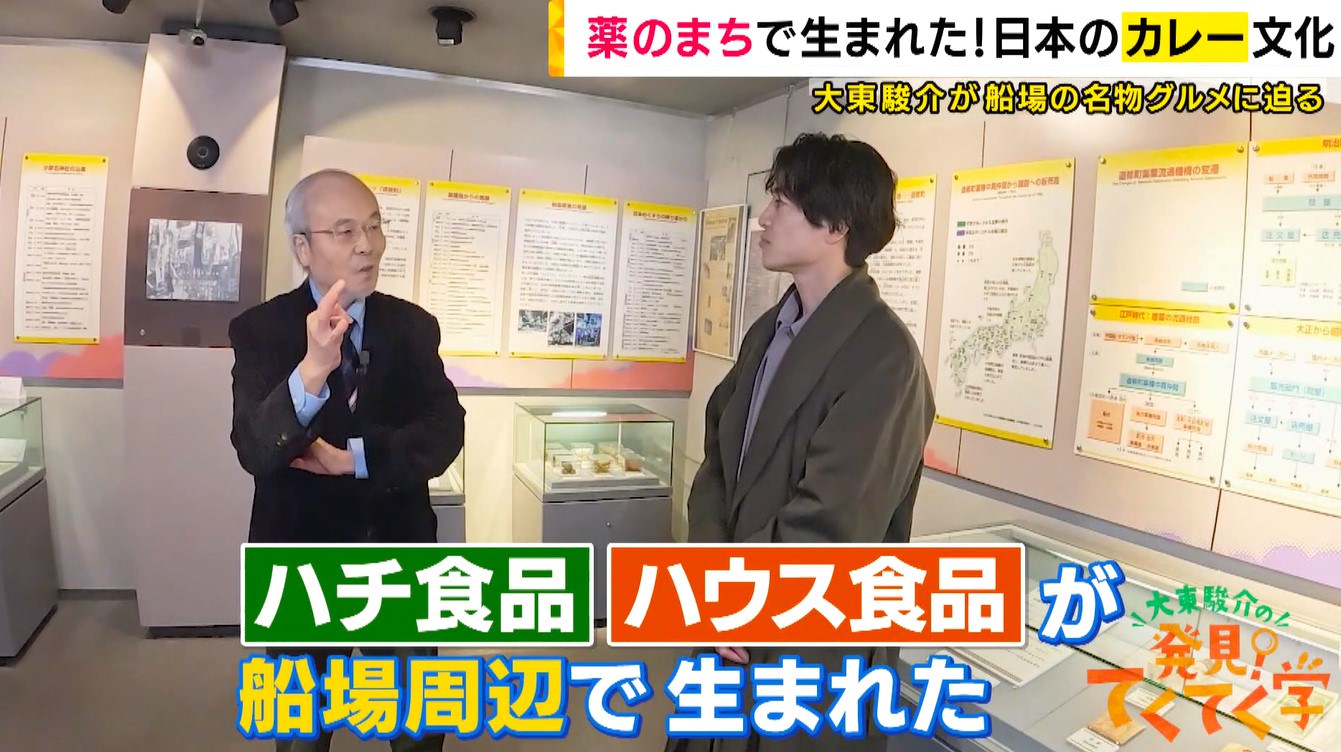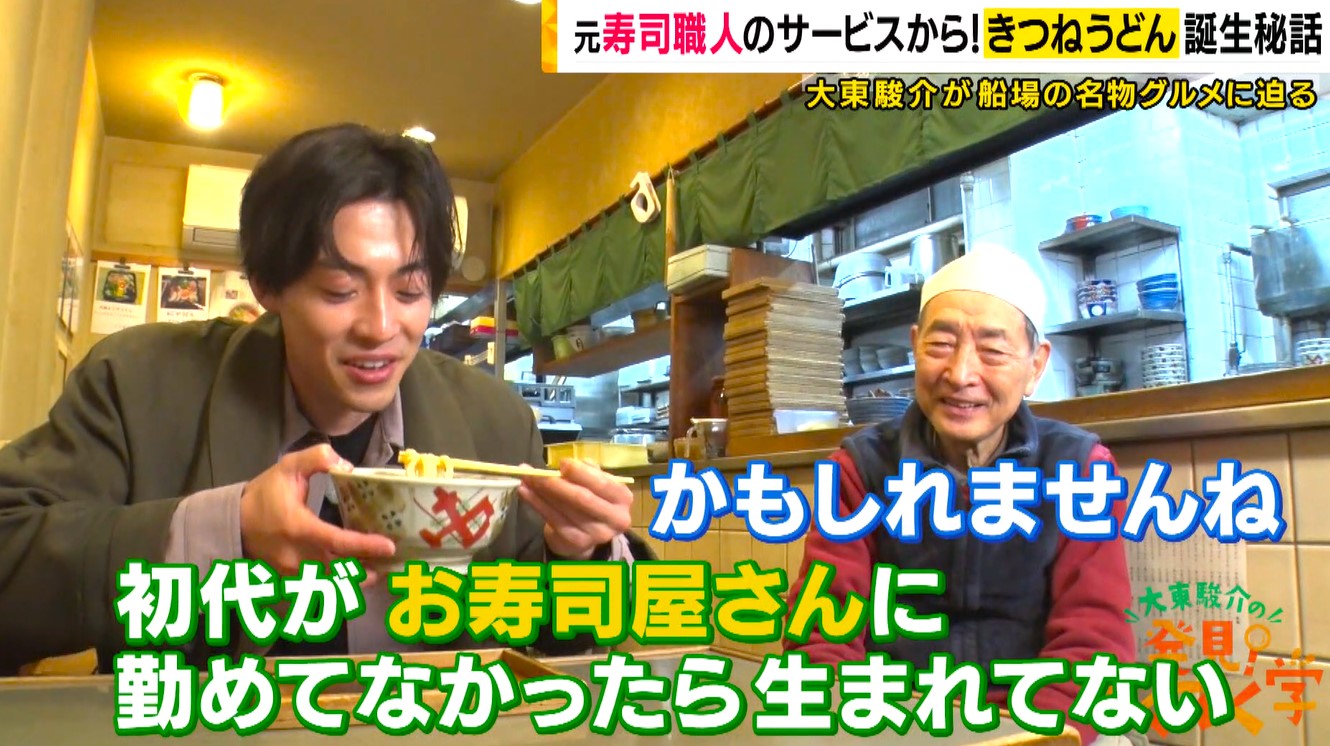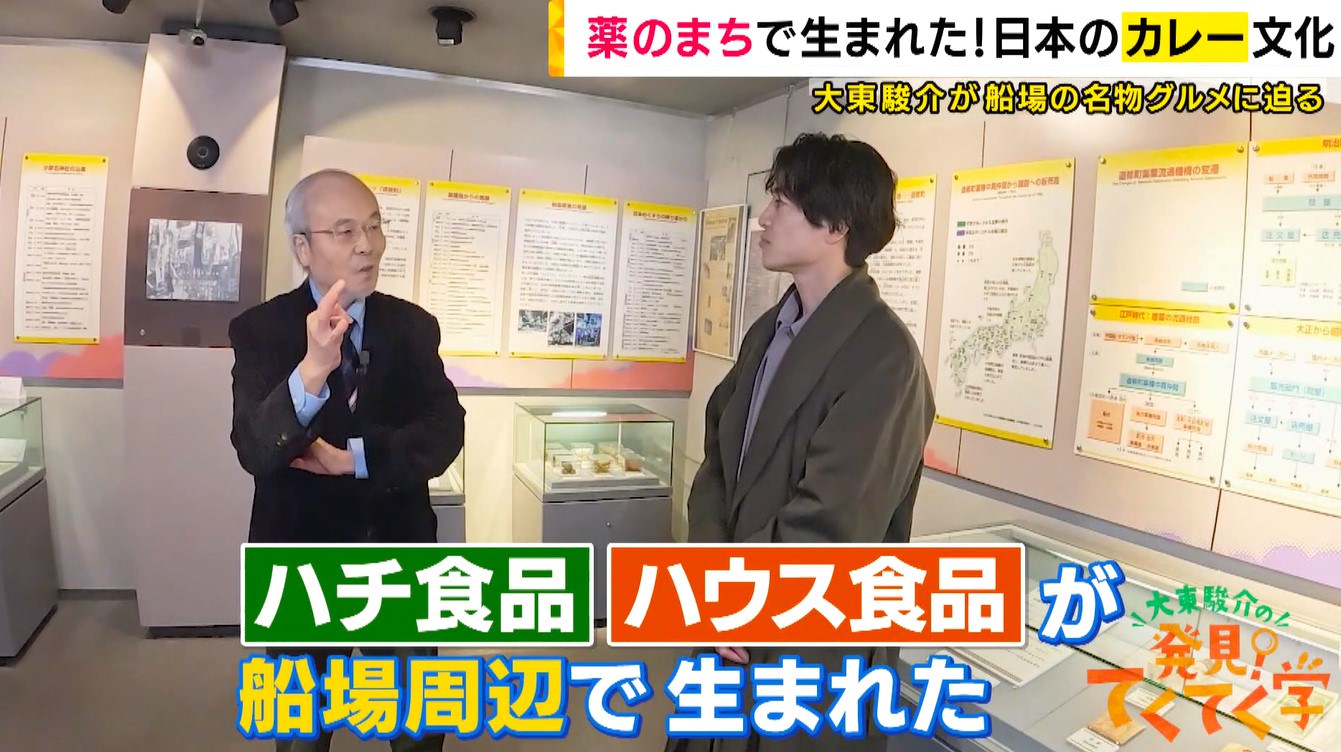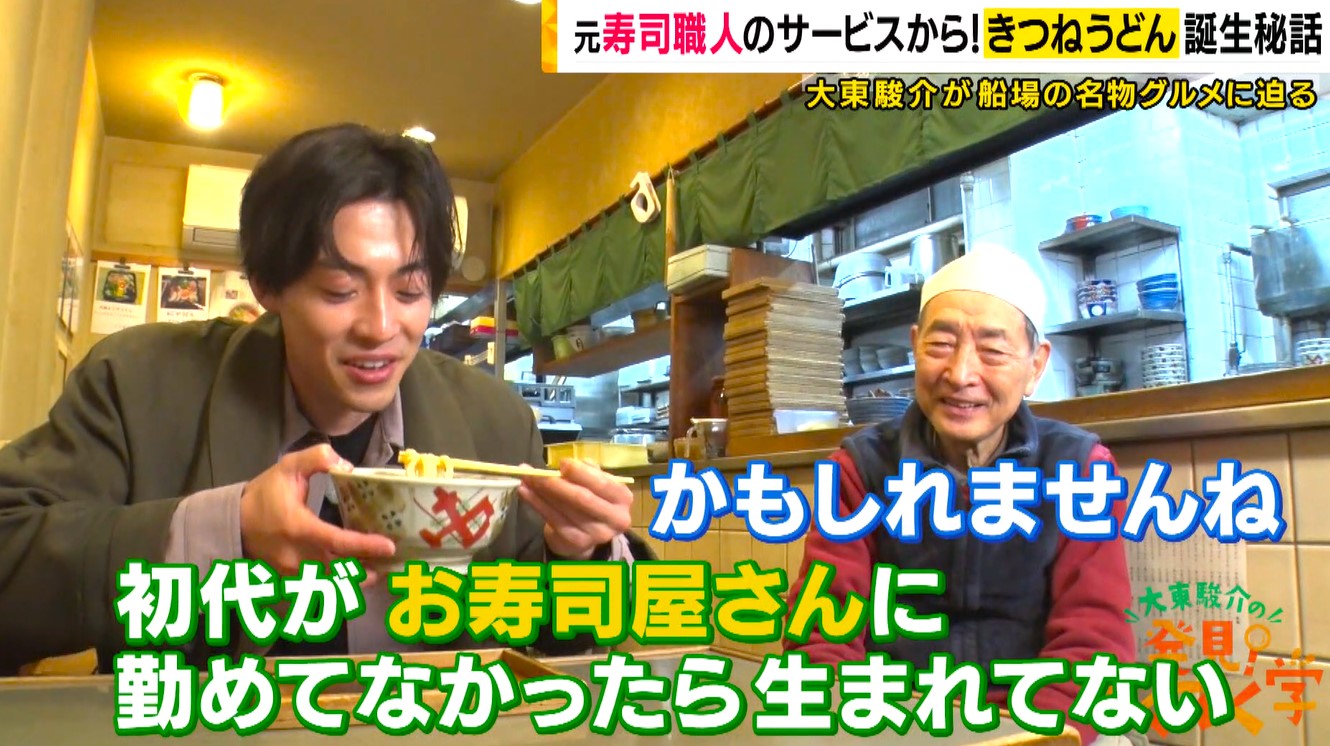きつねうどんとカレー“2大グルメ”が誕生した街「たまらんぐらいうまい」はしごで食べまくり【大東駿介の発見!てくてく学 関西テレビ「newsランナー」】 2025年03月29日
俳優の大東駿介さんが、関西の街を歩きながら魅力を学ぶ「発見!てくてく学」。
大阪の船場エリアは、多くのオフィスビルが立ち並ぶ一方、戦前から残る貴重な近代建築が集まるエリアでもあります。そんな船場から全国へと広まった、「2つの名物グルメ」があります。
■薬の街で生まれた「日本のカレー」文化
日本の医薬品産業発祥の地といわれる道修町(どしょうまち)。武田薬品工業や塩野義製薬など、多くの製薬会社が軒を連ねています。その歴史を知り尽くした、くすりの道修町資料館館長の深澤恒夫さんに話を聞きました。
【深澤恒夫さん】「道修町の薬の歴史は300年。当初、長崎に入ってきた薬がここで検査して、合格したものしか全国に売れなかった」
江戸時代の道修町には、124軒もの薬を扱う薬種問屋が密集していたそうです。
そして日本のカレー文化は、実は大阪の船場から生まれました。深澤さんによると、カレーは明治の初めにイギリスから入ってきたのですが、大変高価なものでした。
道修町の近くで薬種問屋を営んでいたハチ食品の創業者・今村弥兵衛は、蔵にしまっていた漢方薬が当時海外から輸入されていたカレーの匂いに似ていることに気づきました。ウコンなどの香辛料を自ら調合して作られたのが、日本初のカレー粉とされています。
また船場の薬種問屋で働いていた浦上靖介は、ハウス食品の前身となる「浦上商店」を創業。大正15年にカレー粉「ホームカレー」の販売を始めました。そして昭和38年には、ハウス食品を代表する「バーモントカレー」を発売。辛いイメージがあったカレーを子供でも食べられるマイルドな味にしました。
■大阪屈指のカレー激戦区で人気スパイスカレーに感動
大東さんが以前から行ってみたかったという「創作カレー ツキノワ」。
ツキノワのスパイスカレーは和風だしを駆使しているのが最大の特徴。昆布・鰹・いりこなどから丁寧にとったダシをベースに、15種類のスパイスと隠し味に味噌を使ったコクのあるスープです。それをスパイスで煮込んだチキンと合わせて、仕上げにクミンと塩で味を整えて、チキンカレーの出来上がりです。
念願だったカレーにありつけた大東さんは、収録のことも忘れてターメリックライスのおかわりとアイスチャイまでいただいてしまいました。
■すし職人だった店主のサービスから「きつねうどん」誕生
明治26年創業のうさみ亭マツバヤは、「きつねうどん」発祥の店と言われています。
3日間かけて味を染み込ませた大きな揚げと、屋久島の鰹節、北海道の利尻昆布でとったダシは絶品。自家製うどんとの一体感がたまりません。名物のきつねうどんは物価高でもありがたい一杯650円なんです。
マツバヤの3代目店主。宇佐美芳宏さんによると、初代店主はすし屋で働いたことがあり、いなりずしをヒントにきつねうどんができたのだと言います。
創業当時、初代はうどんのサービスとしていなり寿司に使う甘辛く煮た揚げを別の皿にのせて出していましたが、ある客が『うどんの中にお揚げさんをのせて食べたらめちゃめちゃうまいで』と言い出し、これが評判となって、うどんに揚げをのせて出すことになったのです。
かつてうどん屋にはかぜ薬が置かれていて、うどんと一緒に口にすることで効率よく摂取することができたのだそうです。「うどんや風一夜薬」という薬が明治9年の大阪で誕生し、この薬と熱々のうどんを食べて一晩ぐっすり眠るのが早期治療法とされていました。「かぜをひいたら、うどん屋に駆け込んで治す」というのがなにわの文化として全国にも広がったのです。
【大東駿介さん】「子供の時、そういう印象だった気がする。体調悪いから優しいもん出すという感じでしたよね」
▲大東さんの“発見”の全ては、動画でじっくりお楽しみください。
(関西テレビ「newsランナー 大東駿介の発見!てくてく学」 2025年3月20日 木曜日放送)