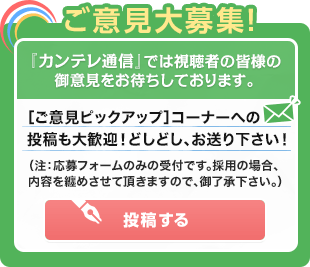11月17日(日)
ご意見ピックアップ
『カンテレ通信』では皆様からのご意見をお待ちしています。番組でご意見が採用された方には、月曜日よる10時から放送しているドラマ「モンスター」などの、カンテレ特製グッズを差し上げます。
『ニュース』 (電話/男性)
-
マスコミは被災地でよくインタビューをしているけど、その前に復興作業を手伝ったらどうかと思う。
-
報道センターの回答
取材者としても、そうした葛藤を感じることはしばしばあり、実際に取材の合間に何らかのお手伝いをすることもあります。しかし、取材者が被災地に入る目的は被災地の状況を多くの人に伝えることです。もし現地からの報道がなければ、被災地の状況への関心は薄れて、復旧や復興の歩みにも影響します。重大な出来事を記録して多くの人にお伝えすることが報道の役割です。ただし、被災地の苦しい状況を他人事のように捉えたり、興味本位にみえるような伝え方ではいけませんし、被災地に大きな負担をかけてしまうような取材方法も避けるべきです。被災者の生の声をお聞きするインタビューでは、取材者側の態度や質問内容が、報道の本旨に沿うことが重要です。
-
コメンテーターから
しまだあやさん
「現地の状況を伝える」ということは、私も大事だと思っています。私は東日本大震災の時に4年間ほど、大阪と現地の2拠点生活をして、現地の高校生100人くらいとともに過ごすということをしていました。その時に、「取材の受け方、あり方」を彼らとよく話すことがあったんですけど、印象的だったのが「被災者」「被災地」と、ひとくくりにされるのではなくて、「一個人の名前」を呼んでくれたり、「あなたの街の好きなところはどんなところ」と聞いてくれたりなど、寄り添うような取材をされると、うれしかったと話していました。そして、取材への答え方についても、「もうちょっと元気になったらウチの街にはおいしいものがいっぱいあるし、それを食べに来てもらうためにも、私たちがまず町のことを伝えるっていうのが大事。だから、いつか町を訪ねてもらって、おいしいものを食べて、支援を超えて街を好きになってもらえたら、それが一番うれしい」と言っていたことがすごく心に残っています。
飯田豊さん
災害報道において取材者がどういうふうに振る舞うのかは、テレビが発明されるよりも前から議論されていて、ジャーナリストの倫理に関わる大きな問いだと思うんです。報道センターの回答はそうした議論の到達点を踏まえて、端的に説明されている、いわば模範解答だと思います。お電話でいただいたご意見ということで、かなりシンプルにまとめられているんですけど、「復興作業を手伝っていないことを責める」というよりも、「被災者に負担をかけたり、傷つけたりするようなインタビュー」を問題にされているのではないかと理解しました。心に傷を負った被災者の方にインタビューすることが、確かに二次被害につながりかねないことはありますし、逆に最近は、被災地を取材した記者の方が、心的外傷を負うリスクが高いことも指摘されています。そういった観点も記者教育の中に、しっかり取り入れてもらいたいと思います。
『とれたてっ!』 (メール/50代/女性)
-
毎日、見ています、カンテレの番組が好きです。ただ、「とれたてっ!」のコメンテーターや番組担当者の紹介で、「○児の父または母」という紹介は必要か?と思います。これまでの仕事のキャリアについて(元海外支局長、元海外特派員など)は紹介があっても納得ですが、子どもがいるかいないかを表記する必要はあるのでしょうか。
-
情報制作部の回答
スタジオに出演しているコメンテーターや解説担当者の紹介では、その人のバックボーンを知っていただくことが大切だと考えています。一般的に経歴を知られているわけではない人が、どういった立場でコメントしているのかを知ったうえでご視聴いただくほうが、より理解が深まると考えているからです。そのため、「元海外支局長」だったり、「元議員」、「大学教授」、「医師」などと同様に、「○児の父または母」ということも、その人の立場を知っていただくために表記することがあります。例えば、「米が不足している」というニュースを扱う場合に、「子供が2人いる親」と「一人暮らしの成人」とでは、必要な米の量も違い、米不足への受け止め方も変わってくると思いますので、そのあたりも分かった上でご覧いただきたいとの思いから、このような表記をしています。
-
コメンテーターから
飯田豊さん
僕自身は「二児の父」ですが、この番組(カンテレ通信)では「メディア研究者」という立場でコメントしていますので、(「二児の父」ということが)テロップに載ることはないです。なぜかというとメディア研究者という観点からコメントしたつもりが、父親という立場を踏まえた見解であると誤解されると困るからなんですね。ただ、その反面、SNSのプロフィール欄などを見ていますと、自発的に家族構成などを書かれている方もいらっしゃいますし、それが自らの社会的な活動と不可分に結びついている場合もあると思うんです。ですからコメンテーターの場合も、「父」「母」という立場をあらかじめ明示しておくことが、コメントするさいの助けになることもあるかもしれませんので、ご本人が自発的に、あるいは制作者との合意の上で載せること自体は、個人的には「あり」かなと思います。先ほどの回答に対しては、表記の是非自体よりも、理由の説明に引っ掛かる部分がありました。コメ不足のことが例に挙げられていましたけども、例えば子どもがいても買い物や炊事を担当していないかもしれないし、子どもはいなくても親を養っているかもしれないわけで、本人が言わない限り、視聴者にはそこまでわかりません。それにもかかわらず、「二児の母」と表記するかしないかで、回答の説明にあった通り、「視聴者の受け止めが変わる」と制作者の側が思っているのだとすれば、たとえ本当にそうだとしても、それは望ましいことなのでしょうか。「父」「母」という立場“だけ”にフォーカスしていることの妥当性については、しっかり考えてもらいたいと思います。
しまだあやさん
言葉っていうのは文脈によってだいぶ印象が変わるものですから、いちがいに「こう」とは言えないんですけど、例えば(そのときの話題が)子どもたちとの物語ありきのテーマだったならば、違和感はそんなにないかなと思っています。もしも自分が同じ「二児の母」だった場合に「二児の母」のロールモデルともなりえるわけですから、背中を押される方もいるんじゃないかと思います。だけど文脈の部分と(「○児の父、母」という)言葉を使われている部分が離れてしまえばしまうほど、違和感が生まれるのかなと思っていて、例に挙がっていたコメ不足の話であれば、肩書で端的に紹介するのではなくて、そのお話が振られるタイミングで、例えば「○○さんは去年、お子さんが中学に上がられたそうですけど、その観点ではどうですか」といったような、ちょっと物語を添えてお話しすることで、「ストーリー、バックボーンを伝えたい」という意図であれば、そちらの方がより視聴者には伝わるんじゃないかなと感じました。
カンテレACT
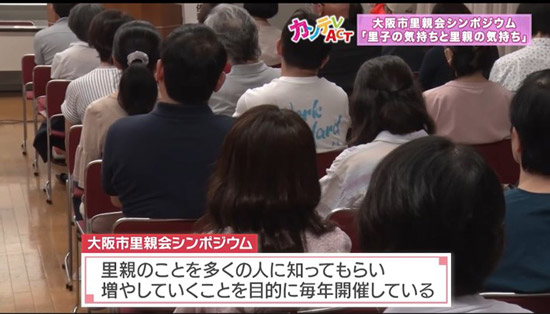
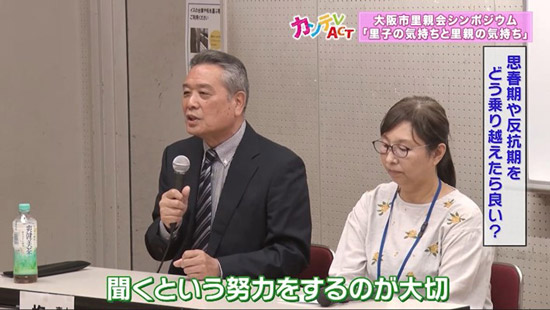

インフォメーション
次回予告
-
『カンテレ通信』は皆様のご意見をお待ちしています。
次回の『カンテレ通信』は、2024年11月24日(日)あさ6時30分放送です。